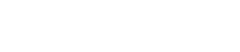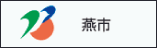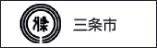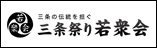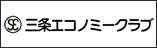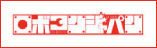理事長所信

理事長メッセージ
【はじめに】
近年、社会全体がかつてないほどの変革期を迎えています。デジタル化の進展、経済のグローバル化、そして予測できない自然災害やパンデミックの影響により、私たちの生活や仕事のあり方は劇的に変わりました。このような変化の中で、多くの人々が未来に対する不安や閉塞感、そして、自分一人で解決する力の限界を感じています。この燕三条地域も例外ではありません。人口減少や経済の停滞といった課題が顕在化する中、地域社会における新しい価値観や活力の創出が急務となっています。私たち燕三条青年会議所もまた、この時代の変化に直面し、これまでの取り組みだけでは解決できない新たな課題に挑む必要があります。地域社会の活力を取り戻すためには、エンターテインメント、グローバルな視点、人間力を基盤とした新たなアプローチが必要です。また、これらを実現するためには、メンバーの育成と会の人員拡大も極めて重要な要素であると考えます。燕三条青年会議所は、燕三条地域で県央中核市の誕生を目指し、燕三条市の実現に向けて市民の意識を変革し続ける唯一無二の団体です。私はこの夢を掲げた素晴らしい団体に所属し、青年時代を過ごせていることに誇りと自信を持っています。しかし、私たちが所属する燕三条青年会議所がどのような団体であり、何をしている団体かという認知は十分に高まっているでしょうか。また、所属している会員の皆さんは、自分の活動を会社の仲間や家族に自信を持って話せているでしょうか。私たちが「燕三条青年会議所って何をしている団体ですか」と問われるようになったのはいつからでしょうか。そして、燕三条市の実現が難しいと感じるようになったのはいつからでしょうか。もし私たちが目標を達成できないと感じているのであれば、それは私たちが過去の先輩たちが成し遂げたこと以上に、何かを達成していないからではないでしょうか。まだやり遂げていないこと、やらなければならないことがあるのではないでしょうか。だからこそ時代のニーズを捉え、事業の目的と手段を明確にし、運動・活動を創造し、しっかりと検証・改善を繰り返して挑戦し続けることが必要です。考えるだけでなく、まず行動することが大切です。先達が築いてきた歴史や伝統を継承するだけでなく、進化のための新たな挑戦をし続けなければなりません。
2025年度を進化の年と位置づけ、私たちが住み暮らす「燕三条」の可能性を追求し、変化を恐れず、青年らしく積極果敢に挑戦していきましょう。感謝の心を持って誠を尽くし、志高く、豊かな「燕三条」の未来を共に切り開いていきましょう。
【エンターテインメントを通じた未来を創造する】
エンターテインメントは単なる娯楽にとどまらず、人々の心を動かし、感動を共有する強力なツールです。燕三条地域は、人口減少や若者の流出といった深刻な課題に直面しています。これらの課題を解決するために地域の魅力を再発見し、それを内外に発信することが必要です。音楽や演劇、スポーツ、アートなど、さまざまな分野での活動を通じて地域社会に新たな活気をもたらし、一体感を生み出すことができます。また、地域ネットワークを活かしたフェスティバルやアートイベントは地域内外の人々に燕三条の魅力を伝える絶好の機会であり、観光産業を含む地域全体の活性化にも寄与します。さらに、世代を超えた交流の場を提供することで市民同士の絆を深め、地域社会の一体感を強化していきます。笑い、学び、感動を共有するこれらの場が市民一人ひとりの成長と地域への貢献を促し、明るい未来を創造する原動力となるのです。私たちはこうした活動を通じて、燕三条地域をより豊かで輝かしいものにしていくことを目指しています。皆さんの積極的な参加を期待し、ともに新たなステージを創造し、地域の未来を切り開いていきましょう。
【人間力を育み未来を創造する】
より良い地域であり続けるために人間力の重要性を感じるものだと思います。人間力とは、他者の心を動かし、社会問題に積極的に取り組む力です。この力は、メンバーや市民が他者と協力し、共に学び合いながら社会に積極的に貢献する過程で発掘され、育まれます。燕三条地域が直面している課題は人口減少や地域経済の停滞だけでなく、若者の地域離れや地域の一体感の欠如といった問題も含まれます。こうした課題に対して、私たちは人間力を育む取り組みを通じて地域社会の活力を取り戻し、未来を切り開いていきます。また、様々な方との対話の場を設けることで地域全体の一体感を高め、互いの理解を深めることを目指しています。これらの取り組みによってメンバーや市民は新しい視点を学び、具体的な行動に移すことができ、地域社会にポジティブな影響を与えることができます。さらに、これらの活動を広く発信することで参画意識を高めます。人間力溢れる人々の活躍により、各個人が自己の能力を信じ、変化を恐れず新たな挑戦を続けることが重要です。私たちは現状に満足することなく、常に新しい目標に向かって前進します。これにより、地域と未来をより豊かで輝かしいものにしていきます。皆さんの積極的な参加と挑戦が、この動きを加速させるでしょう。さあ、人間力を発掘し育み、人財の未来を切り開きましょう。
【グローバルな視点で未来を創造する】
燕三条地域の発展と成長は、国際社会との深い関連性に支えられています。世界各国との連携や共栄は、私たちの地域が直面する様々な課題に対処するための新たな価値観や刺激を受け取る基盤となります。このグローバルな視野を持つことは、地域社会の未来を豊かにするために不可欠です。燕三条地域は古くから金属加工産業が盛んな地域であり、国際市場でも高い評価を得ています。このような地域資源を活かし、国際的な展示会への参加や海外との技術交流を積極的に行うことで地域産業の発展を促進し、世界に向けた発信力を強化しています。また、地域の企業と連携し、外国人労働者や観光客を受け入れるための多文化共生の取り組みの中から地域に必要なものを見出します。多様な文化を尊重し、共に成長する姿勢を持つことで地域の活力を引き出し、地域社会の一体感を高めています。このような活動を通じて、私たちは国際的な視野を広げ、グローバルな課題に対する理解を深め、地域の成長に貢献していきます。私たちが住む「燕三条」の発展のためには、国際的なつながりを活かし、時代の変化に迅速に対応する必要があります。地域外の変化に敏感であり、地域が直面する課題に積極的に対処しようとする姿勢が重要です。私たちの地域が国際社会でさらに影響力を持つために努力しましょう。皆さんの積極的な参加と協力が、これらの取り組みを成功に導く鍵です。さあ、グローバルな視点を持って行動し、地域の未来を切り開きましょう。
【新たな仲間と遊び心を持って未来を創造する】
私たちの組織は、一人ひとりの「個」が結集して成り立っています。組織の力を高めるためには、メンバーそれぞれが遊び心を持ち、主体的に参画し、深い交流を図ることが不可欠です。私たちの組織には無限の可能性が秘められており、その力を最大限に引き出すためには、「個」の力を結集し、互いに理解し合い、友好的なつながりを築くことが必要です。「遊び心」とは創造性や柔軟な思考を育むための精神です。組織が新しいアイデアやアプローチを模索する際に、固定観念にとらわれず、自由な発想で挑戦することができるようにする力が「遊び心」であると考えます。これによって、従来の方法では解決できない問題に対して新たな視点を持ち込み、組織の活性化や成長を促進することができます。また、メンバー同士が形式に縛られず、自由な発想で意見を出し合える場を設けます。こうした場では、あえて「遊び心」を持って新しいアプローチや取り組みを試すことで、組織全体に新たな活力が生まれます。私たちは、会員拡大と組織の活性化に向けた新たな取り組みに挑戦します。この挑戦を成功させるためには、多様な価値観の受け入れと共有が重要です。遊び心を持つことで異なる背景や視点を持つメンバー同士が自由に意見を交換し、互いの考えを尊重し合う文化が育まれます。遊び心を取り入れたアクティビティを通じて、メンバーが新しいスキルや知識を楽しみながら習得し、次の挑戦に向けたモチベーションを高めることができます。組織は挑戦を恐れず、遊び心を忘れず成長し続けることで活性化し多くの仲間を迎え入れます。さあ、多くの仲間と共に、強固な組織で未来を切り開いていきましょう。
【組織の未来を創造する】
現代社会の成長に伴い、組織運営においても革新的なアプローチが求められています。燕三条青年会議所ではこの変化に対応し、内外に高い存在感を示すため、階層的な構造だけでなく、横断的な繋がりや情報共有を重視した組織体制の強化を進めています。この目的のために、現役メンバー向けの情報共有システムを見直し、より包括的なツールと運営体制を整えることで、情報に容易にアクセスし、積極的に参加できる環境を整えることが重要です。さらに、運動の効率化を図るために新たな運営体制並びにデジタルツールや最新テクノロジーを積極的に活用します。これにより情報共有とコミュニケーションの円滑化が図られ、時代に即した効果的な組織へと発展させます。また、燕三条青年会議所の社会的プレゼンスを高めるためには外部との連携も不可欠です。私たちの活動や想いをしっかりとOBの方に伝え、繋がりを深め、ネットワークを拡大することが重要です。これにより組織の声が広く認知され、意思決定や政策に対する影響力を向上させることが可能になると考えます。更なる繋がりの拡充を目指し、より広範なパートナーシップを築いていきます。皆さんの積極的な参加と協力が、これらの取り組みを成功させる鍵です。共に力を合わせて、燕三条青年会議所をより強固で活力ある組織にしていきましょう。一緒に新たなステージを切り開き、組織の未来を切り開いていきましょう。
結に
私たちは決して一人で生きているのではなく、祖先や両親、そして多くの人々とのつながりの中で今ここに存在しています。このつながりを大切にし、私たちの限られた人生をどう生きるかが重要です。関わるすべての人々と機会に感謝し、この一度きりの人生を豊かに生きていきましょう。これからの燕三条地域を支えるためには、私たち一人ひとりが「個人の修練」を通じて成長し、社会に対して「奉仕」の心を持ち、そして「世界との友情」を大切にすることが必要です。これこそがJAYCEEの精神であり、私たちが目指すべき姿です。地域社会が直面する課題を乗り越え未来を切り開くためには、エンターテインメント、グローバルな視点、人間力、遊び心、そして強固な組織運営が不可欠です。私たちはこれらの要素を基盤とし、変化を恐れず、新たな挑戦を続けていきます。それぞれが持つ力を結集し、互いに支え合いながら、明るい未来を創造するために歩んでいきましょう。私たちが住む「燕三条」のために、国際的な視野を持ち、地域の発展と持続可能な未来を実現するために努力することが求められています。私たちはこれまでの歴史や伝統を継承しつつ、時代のニーズに応じた新たな価値を創造し、地域の活力を引き出すことで次の世代へと希望を繋げていきます。燕三条青年会議所は、地域と人と世界を結びつける唯一無二の団体です。私たちの力を結集し、未来を見据えた行動を起こすことで、共に明るく豊かな燕三条を実現しましょう。共に手を取り合い力を合わせて、この地域の未来を切り開いていきましょう。
Connecting the Dots
点と点を結び新たな未来を切り開きましょう
【運動方針】
(1)「燕三条」の可能性を追求することで市民を魅了し、地域の新たな魅力を創造する運動(エンターテインメントの力
・エンターテインメントを活用し、音楽、演劇、スポーツ、アートなどの多様な文化活動を通じて地域に活気を生み出し、市民同士の絆を深める。
(2)これからの「燕三条」を担う人間力溢れる人財を発掘・育成し、地域の活力を高める運動(人間力)
・人間力を育むための対話や教育の場を提供し、メンバーや市民が新しい視点を学び、創造性を発揮できる環境を整えることで、地域の未来を切り開く。
(3)「燕三条」市民としての誇りを醸成し、国際社会への躍進を支える運動(グローバル)
・燕三条地域の国際的な競争力を強化するため、グローバルな視点を持ち、国際市場での発信力を高める。また、多文化共生を推進し、地域の一体感を育む。
(4)燕三条」の次代のリーダーとなる未来のJAYCEEを発掘・拡大・育成する運動(組織増強)
・新たなメンバーの参加を促し、組織の活性化を図るために、創造的で柔軟な思考を持つ「遊び心」を大切にし、自由な発想で挑戦する文化を醸成する。
(5)効果的に情報を発信・共有するとともに、「燕三条」青年会議所の一体感を醸成し、有機的なつながりを創造する運動(事務局)
・組織体制の見直し並びに、情報共有システムの見直しと強化を図り、メンバーが積極的に活動に参加できる環境を整備し、外部との連携を強化してネットワークを拡大する。
(6)新たな戦略や施策のあらゆる可能性を模索し、「燕三条」の未来を創出する運動(PT)
・革新的なアプローチを取り入れ、今まで行ってきた実績を活用して、時代に即した効果的な事業を実現する。